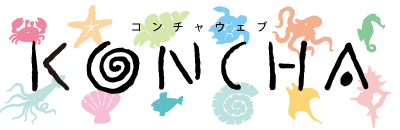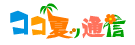歴史
パラオにはミクロネシア系の先住民族が古代から住んでおり、約3000〜4000年前には定住が始まっていたと考えられています。インドネシアやメラネシアの影響も受け、ミクロネシアの中でも早く文明が発展した地域です。
16世紀以降、ヨーロッパ人が来航し、1783年にはイギリス船アンテロープ号の座礁をきっかけに、パラオが西洋に知られるようになりました。
1885年にスペインの植民地となり、カトリックの布教が始まりましたが、1899年にはドイツに売却され、リン鉱石採掘などの産業が導入されました。1914年、日本がドイツ領を占領し、1920年には国際連盟の委任統治を受けて南洋庁を設置。日本人の移住が進み、1935年には人口が2万5千人を超え、パラオは地域の中心地として発展しました。1944年、ペリリュー島で日米の激戦があり、多くの犠牲者が出ました。戦後はアメリカの施政下に入り、1947年には国連の信託統治領となりました。
1981年に憲法が制定され自治政府が発足。1994年10月1日に正式独立し、同年12月に国連加盟。
現在は観光業を中心に発展を続ける独立国家です。
【年表】
約4000年前:パラオに人類が定住を開始
1543年:スペイン人ルイ・ロペス・デ・ビリャロボスがパラオ近海に到達
1783年:イギリス船アンテロープ号が座礁、船長ウィルソンが現地首長と交流
1885年:スペインがパラオを植民地化
1899年:スペインがパラオをドイツに売却
1914年:第一次世界大戦勃発、日本がパラオを含む南洋諸島を占領
1920年:国際連盟が日本の委任統治を承認
1935年:パラオの日本人人口が約25,760人に達する
1944年:ペリリュー島で日米の激戦が展開
1947年:国連の太平洋諸島信託統治領としてアメリカの施政権下に
1981年:憲法制定、自治政府発足
1994年10月1日:アメリカとの自由連合盟約により独立
1994年12月:国連加盟
宗教
パラオでは、19世紀以降のスペイン、ドイツ、日本、アメリカによる植民地支配を経て、キリスト教が広く浸透しました。
現在、パラオの人口の約80%がキリスト教を信仰しており、カトリックとプロテスタントが主流です。各村には教会があり、地域社会の中心的な役割を果たしています。
言語
パラオの公用語は パラオ語と英語です。パラオ語はオーストロネシア語族に属し、約15,000人が話します。日常会話ではパラオ語が使われますが、教育や行政、観光業では英語が広く用いられています。さらに、パラオのアンガウル州では 日本語が公用語として憲法に明記されています。これは日本統治時代の影響によるもので、現在でも高齢者を中心に日本語を理解する人がいます。
パラオ語には「ダイジョブ」「ゴメン」「オキャク」など、日本語由来の語彙が約1,200語以上存在するとされており、日本語の影響が色濃く残っています。
人口・人種
現在、パラオの人口は約 17,000人で、国土面積は約460平方キロメートルです。人口の約72%が先住のミクロネシア系パラオ人で、残りはフィリピン系、中国系、日系、アメリカ系などの多民族で構成されています。コロール州には人口の約半数が集中しており、観光業を中心に外国人労働者も多く、国際色豊かな社会が形成されています。